こんにちは、こたちです
私は2023年に本ブログを更新しながら、心臓リハビリテーション指導士を取得しました
当時はtwitter(現X)を通じて皆さんと勉強したり、
本ブログに勉強したことをまとめたりしながら、ゆるっと勉強していました
おかげで試験本番も、特に焦ることなく、合格できたと確信を持って試験を終えることができました
しかし、それはあなたが優秀だったからでしょう、と思われるかもしれませんが、
私は普通の一般的な偏差値の大学を卒業した普通のPTです
普通のPTが自信を持って心リハ指導士に合格できた、勉強方法についてまとめました
勉強仲間を作る
勉強するには仲間がいた方が良い、という研究は多く存在します
一つは理解が深まること
例えば、仲間に自分が勉強した部分を説明することで、本当に理解できているかがわかります
当然、わからないところを相談したり、語呂合わせを共有することもおできるでしょう
理解を深めるには、仲間の存在は大切ですね
もう一つは、モチベーションを維持できることです
お互いに折れそうな心を支え合うことで、勉強を続けられることを経験した方は多いでしょう
私には同僚が1人、同じ年に受験するスタッフがいました
同僚の存在は非常に大きく、勉強の後押しにもなりました
また「X」でも心臓リハビリアカウントを作って、仲間を作りました
その仲間とは今でも学会で会うこともあります
とにかく、まずは1人で受験しないことです
1人で勉強することと、1人で受験することは違います
1人でも多くの仲間と共に、高め合いながら勉強していくことを強く勧めます
“心臓リハビリテーション必携”を一回通り読んでみる
心臓リハビリテーション指導士を受験するには、この本が必読です
「-指導士資格認定試験準拠- 心臓リハビリテーション必携」増補改訂版
価格 6,600円(税込み)
販売元 日本心臓リハビリテーション学会事務局

そして、この本(必携と呼びます)からしか、問題は出題されません
とにかくこの必携をしっかりと読み込むことが大切になります
一度、流し読みで良いので、一通り読んでみることをお勧めします
わからない単語、理解が及ばない部分もたくさんあるでしょう
それでも良いです
2週間ぐらいかけて、ゆっくりで良いです
どの辺りを勉強する必要があるかが、自分がどの辺を勉強すべきかが、
ざっくりとわかってきます
これで下準備は終わりです
直前講習で出た部分をしっかり暗記
一通り、心臓リハビリテーション必携を読んだ状態で、直前講習会に臨みましょう
例年、2週間〜1ヶ月前に、直前講習会が開かれます
2025年7月6日(日)オンラインで開催されるようですね
一昔前は、心臓リハビリテーション学会の開催地で、直前講習会を実施していました
そのため、必ず学会開催地まで出向く必要があり、非常にお金がかかりました
しかし今はコロナの影響から、zoomでも開催となり、受験のハードルも下がりましたね
直前講習会の内容ですが、
試験に出る部分を、ここは試験に出ます、という感じで順番に説明していきます
これほどありがたい講習会はありませんね
しかし、この講習会に出てくる内容は、いわゆる暗記系のものばかりです
例えば、「レジスタンストレーニングの効果」や、「心臓リハビリの適応」などです
つまり、直前講習会で得た知識、覚えるべき部分は、しっかりメモしておき
本当の試験の直前に、しっかり復習しましょう
最後の最後の追い込みで勉強するべきポイントを教えてくれる講習会
これが、直前講習会の意味合いであります
計算問題や画像問題を解く
心臓リハビリテーション指導士試験は時間制限が非常にシビアです。
60分で50問、複数選択ありの試験ですので、1問にかけられる時間は約1分です。
中でも文章問題(症例問題)が約10問は出題される傾向にありますが、単純な記憶問題とは異なり、
回答に時間がかかる傾向にあります。
そこで、文章問題、計算問題、画像を用いた問題にも慣れておく必要があります
ただ、そのような問題は、必携を読んだだけではわかりません
これが、心臓リハビリテーション指導士の難しいところです
もし、お金をかけられる人は、
↓↓ メルカリやnoteで販売している、計算問題集などを購入するのも良いでしょう ↓↓
特に難しいのはMETs計算でしょうか
1 METs=安静時の酸素摂取量(3.5ml/kg/min)
peak VO2の単位=ml/kg/min
この単位さえ覚えておけば、体重を掛け算したりして、なんとか計算できるものです
詳しいところは問題集を購入したり、直前講習会でもVO2/VCO2スロープを学べば、
十分理解できると思いますよ
もう一度、”心臓リハビリテーション必携” を読む
さて、直前講習会が終わり、計算問題などにもしっかり取り組んだ後は、
もう一度、必携を読むことをお勧めします

2回目になると、理解できているところは読み飛ばして良いでしょう
直前講習会や計算問題でわからなかったところ、記憶しきれていないところだけを、
しっかりと読み込んでいきましょう
付箋をつけたりするのは、2回目の読み込みで良いと思います
1回目から付箋をつけていくと、ほとんど付箋だらけの必携になります
2回読んでも覚えきれていないところだけに付箋をつけることで、
最後の最後、数時間レベルの追い込みのところで役にたつでしょう
ラストは直前講習会資料と、必携の付箋部分で追い込み
最後は普通のテストと同じですね
直前に詰め込むべきところをどんどん詰め込んでいきましょう
1,2日〜試験直前は、とにかく記憶力勝負です
赤シートを使うなり、自分で作った単語帳を使うなり、自分のやりやすいやり方で、
どんどん頭の中に詰め込んでいきましょう
ここまで来れば、もはや私のアドバイスなどは不要でしょう
まとめ
いかがでしたでしょうか
- 勉強仲間を作る
- “心臓リハビリテーション必携”を一回通り読んでみる
- 直前講習で出た部分をしっかり暗記
- 計算問題や画像問題を解く
- もう一度、”心臓リハビリテーション必携” を読む
- ラストは直前講習会資料と、必携の付箋部分で追い込み
特に個人的には1の勉強仲間を作ることが一番大切だと感じています
その日の勉強は1人でやらないと集中できないので、1人がいいと思いますが、
わからなくなった時、諦めそうになった時に、仲間が背中を押してくれるはずです
一緒に試験を受けてくれるコメディカルを作っていきましょう
以上、参考になれば幸いです
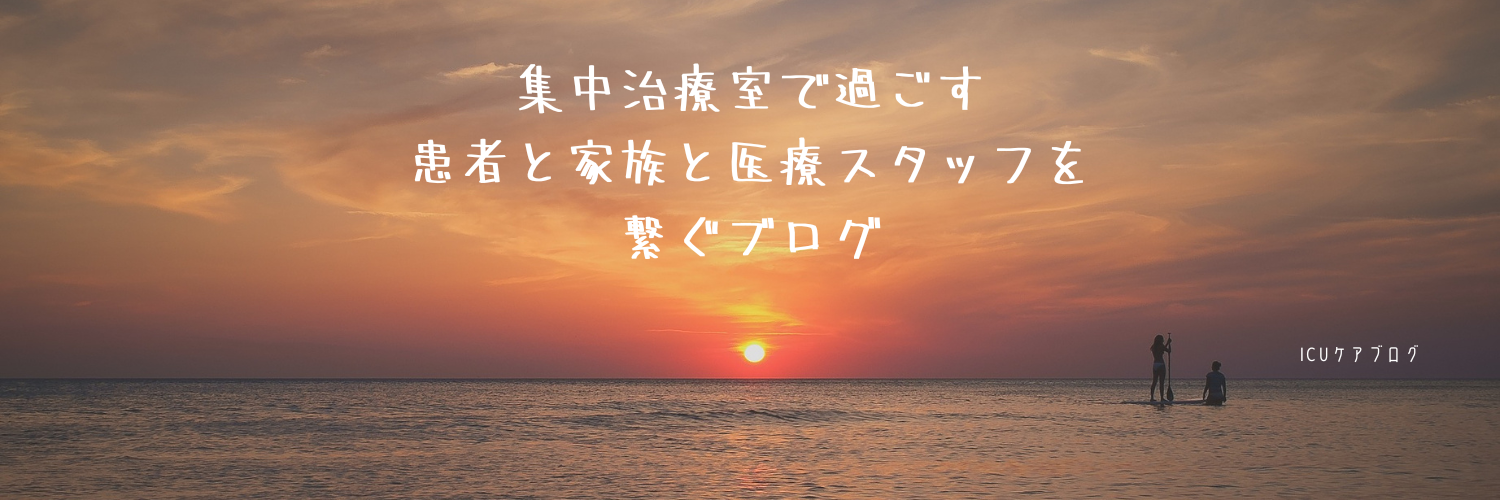
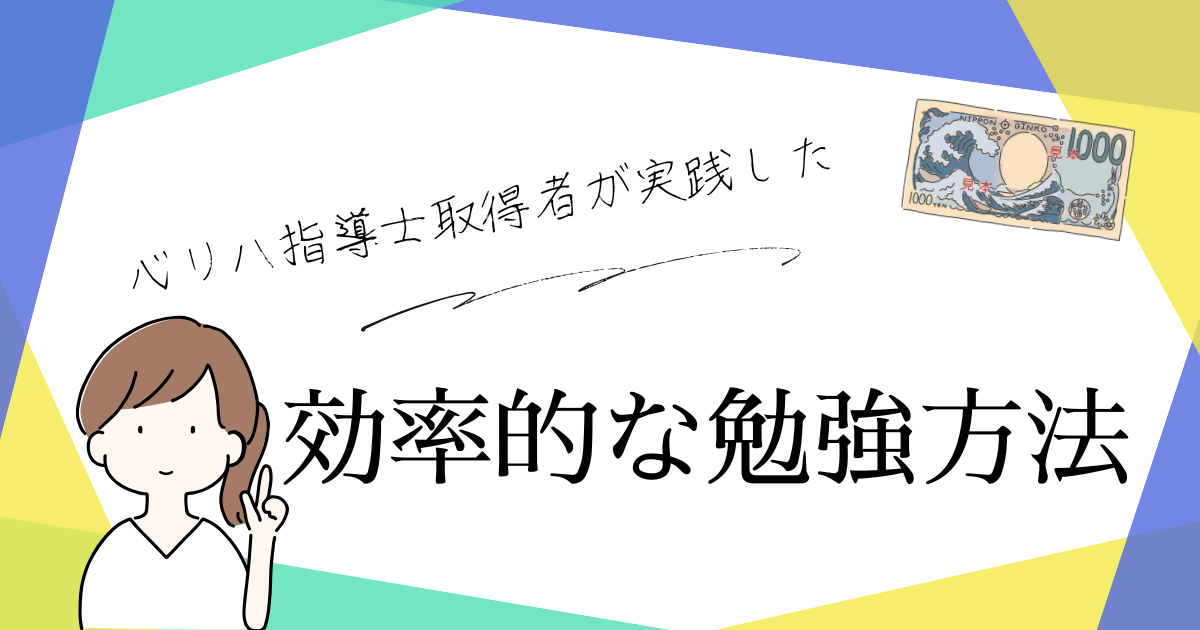

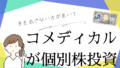
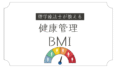
コメント