集中治療室に家族が入院し、面会に行った時、手を握りたい、抱きしめたい、頭を撫でたい、など患者様に触れたい、という感情が何よりも先に出てきます
それは、患者家族としては当然のことであり、愛する家族が苦しんでいる姿を見れば、誰しもがなんとか助けたいと思うはずです
しかし、こんなにたくさんの機械に繋がれているのに触って良いのだろうか、こんなに体が弱っているのに菌が移ったりしないだろうか、私が触ると不愉快な思いをさせるのではないか、そのような葛藤もあるかと思います
しかし、患者家族は、患者様に触れた方が良いのです
それは、患者家族にとっても、患者本人にとってもです
私たち医療者も、管が抜けたりさえしなければ、どんどん触れてほしいのです
本日は患者家族が患者様に触れた方が良い3つの理由と、その注意点について解説します
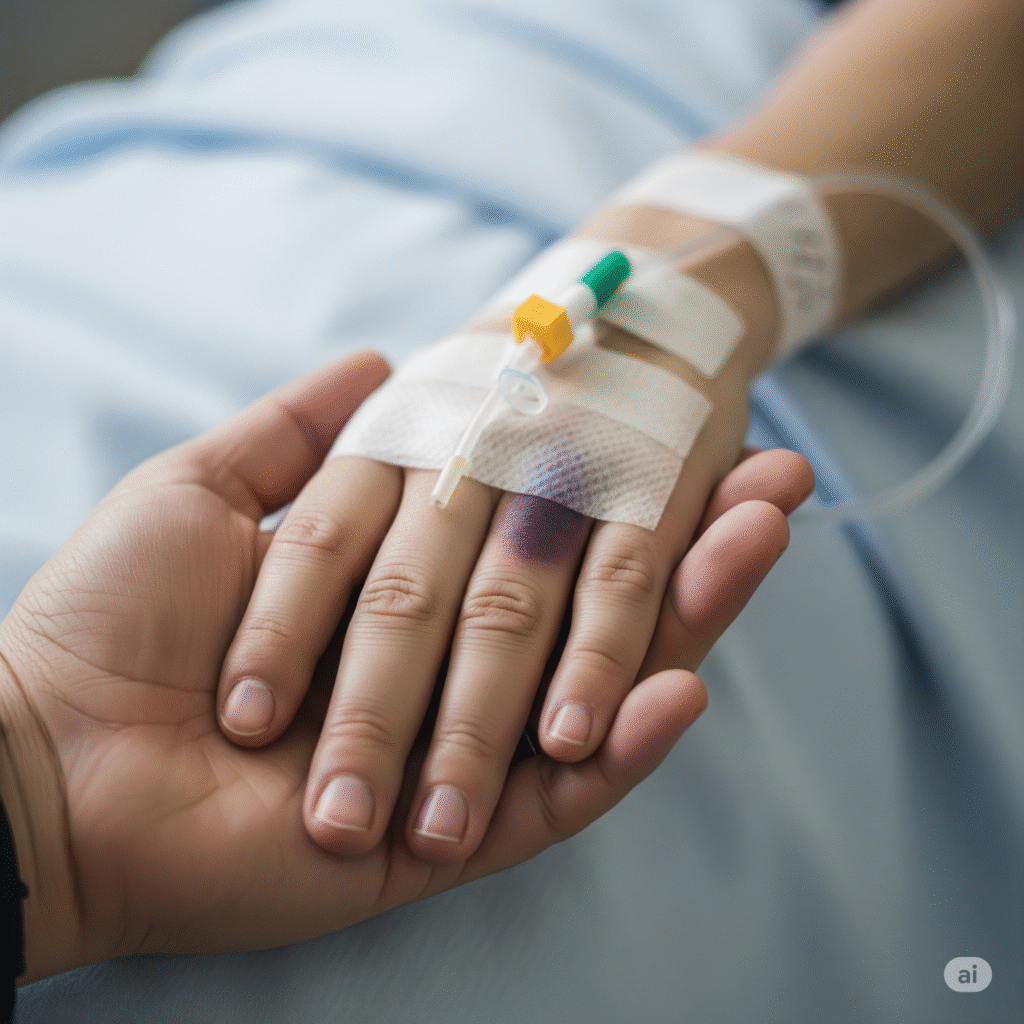
集中治療室の患者は家族に触れられることで治療への意欲が上がる
まずは患者本人の目線で話をします
患者は初めて出会う看護師や医師に囲まれて、日々苦しい治療に立ち向かっているため、不安が募っています
そんな中、苦しいリハビリにも立ち向かわなければならず、精神的に不安定な状態となり、リハビリにも積極的に取り組めない方も一定数いらっしゃいます
このような時に、家族が触れる、励ます、一緒に参加する、という行為は患者のモチベーションを維持するために非常に重要な効果があることが示されています
死への不安や恐怖に立ち向かうことは1人では困難です
もちろん我々医療者も、その不安を少しでも和らげることができるよう、日々努力していますが、家族の存在には敵いません
是非、リハビリ中やそれ以外の時間にも、患者の体に触れ、心を支えて頂ければと思います
家族は、集中治療室の患者に触れることで、不安や恐怖が減る
次に、家族に対するメリットを紹介します
家族が面会に来た時に、苦しそうにしている大切な家族を目にすることは、非常にストレスが高いです
そのような高いストレスに何度もさらされると、家族の心が壊れることがあります
これは家族の集中治療後症候群、post ICU syndrome-family(PICS-F)と呼ばれ、海外でも問題に上がっています
具体的な例を挙げると、集中治療室に2週間入院した家族を毎日面会に来ていた家族が、苦しそうな患者を見ながらも、何もすることができずに後悔していた。その後患者は退院したが、自宅で元気のない姿を見て、集中治療室で苦しんでいる姿を今でも思い出し、その時の辛さと後悔を毎日感じながら生活している。
実際にこのような後悔の念を、その瞬間のみならず、数ヶ月にわたって患者家族を苦しめることもあります
これは、ICUでの苦しい思い出が苦しいままの記憶として残ってしまい、少しでも苦しいこと、例えば息を一瞬止めることで、ICUの苦しい記憶が蘇ってしまう、PTSDのような状態になっていると推定されます
しかし、家族が患者に触れる、声をかける、マッサージする、体をさする、声をかける、そのような行為が、このようなPTSD症状を和らげる効果があることが分かっています
家族が患者のケアに参加すると、家族が不安やPTSD症状を発症する頻度を減らすことができることを示した論文
患者のみならず、家族の心のケアをすることも、我々医療者の使命の一つです
是非、辛い思いをしている時だからこそ、積極的に患者に触れ、声をかけることをお勧めします
集中治療室で働くスタッフは、家族がケアに参加することを望んでいる
最後に、集中治療室で働く、我々スタッフの目線からです
私たちは、家族が治療やケア、リハビリに参加することを心から望んでいます
なぜなら、家族からの声掛け、サポートは患者に生きる意欲を与え、積極的に治療に取り組む姿勢を取り戻すことに、非常に重要だからです
中には、私たちが手伝ったら邪魔なのでは?と感じるご家族もいるかもしれません
しかし、私たちが患者に悪影響を与えない範囲での手伝ってほしいことを一つ一つ説明していきますので、その範疇であれば、どんどん治療に参加してほしいと思います
具体的には以下のようなことになります
- 患者の体を拭く、清拭というケアに一緒に参加する
- リハビリ中の汗を拭う、声をかける、一緒に手足を動かす
- 手を握る、頭を撫でる、さする
- 応援する、励ます
- マッサージをする
このような行為は、決して医師や看護師、リハビリスタッフの邪魔をすることなく、患者の治療やケアに共に参加できることです
そして、これらは患者自身も、リラックスでき、安心して治療に取り組むことができるため、我々スタッフもありがたいことだと思っています
もちろん、忙しさに応じて家族の参加をお断りすることもあるかと思いますが、可能な限り家族のケア参加に協力していきたいと考えているのが、最新のガイドラインでも示されているのです
家族がケア、リハビリに参加することを考慮した初めてのガイドライン(2023年版が最新)
集中治療室で家族が患者に触れる際の注意点
とはいえ、なんでもかんでも触れれば良い、手伝えば良い、というわけでもありません
ここからは、家族が患者に触れる際の注意点を3つ紹介します
管の事故抜去は生命に関わるため要注意
私たちは、患者が無意識に管を抜いてしまわないように、身体抑制、を行うことがよくあります
しかし、身体抑制は家族から見ても気持ちの良いものではありません
家族が来ている時ぐらい、身体抑制を外してあげたいと思っています
ただ、患者が管を無意識に抜くときのスピードやパワーは恐るべきもので、ほんの一瞬で生命に関わる大切な管、例えば人工呼吸器を抜いてしまうことがあるのです
これは家族の責任でもなければ患者の責任でもなく、我々医療者がしっかりと観察していなければならないのですが、ご家族の方にも、そのような状態であることをご理解いただきたいと思います
管が入っている腕をさする、これも触り方を間違えれば管がずれたりテープが剥がれたりすることもあるでしょう
どの部分なら触れて良いか、抑制を外したら患者の手を握っていた方が良いのか、看護師に確認しながら、患者のケアに参加して頂ければと思います
家族が患者のケアに参加することで、患者が不快に感じることもある
亭主関白のご主人によくあることですが、あまり弱っている姿を見られたくない、という方もいます
そのような方に、むやみやたらに家族が触れたり、支えたりすると、患者の自尊心を傷つけてしまうことがあります
患者によっては、自分のイメージを保ちたいと思ったり、自分の姿を恥ずかしいと感じたり、また医療スタッフがやった方が良いのでは?と心配する方もいます
患者の心情や社会的背景を考慮した選択をする必要があるため、ご家族には、病前の性格や考え方がどうであったかなど、教えてもらえると助かりますね
家族が患者のケアに参加することで、家族自身が苦痛を感じることもある
ここまでずっと、家族は患者に触れた方が家族自身のためにいいんだ、というお話をしてきました
しかし、家族の性格や精神状態によっては、かえって積極的に触れない方が良い場合もあるようです
具体的には、患者に触れることで、医療者の邪魔になるのではないか、医療者が行った方が安全で効果が出るのではないか、という懸念があるようです
また、精神的にショックを受けている家族の場合、家族の心理状態をさらに悪化させる可能性もあります
家族がケア、リハビリに参加することの懸念も記載されたガイドライン(2023年版が最新)
これらの注意点も考えた上で、医療者側もご家族と接していきます
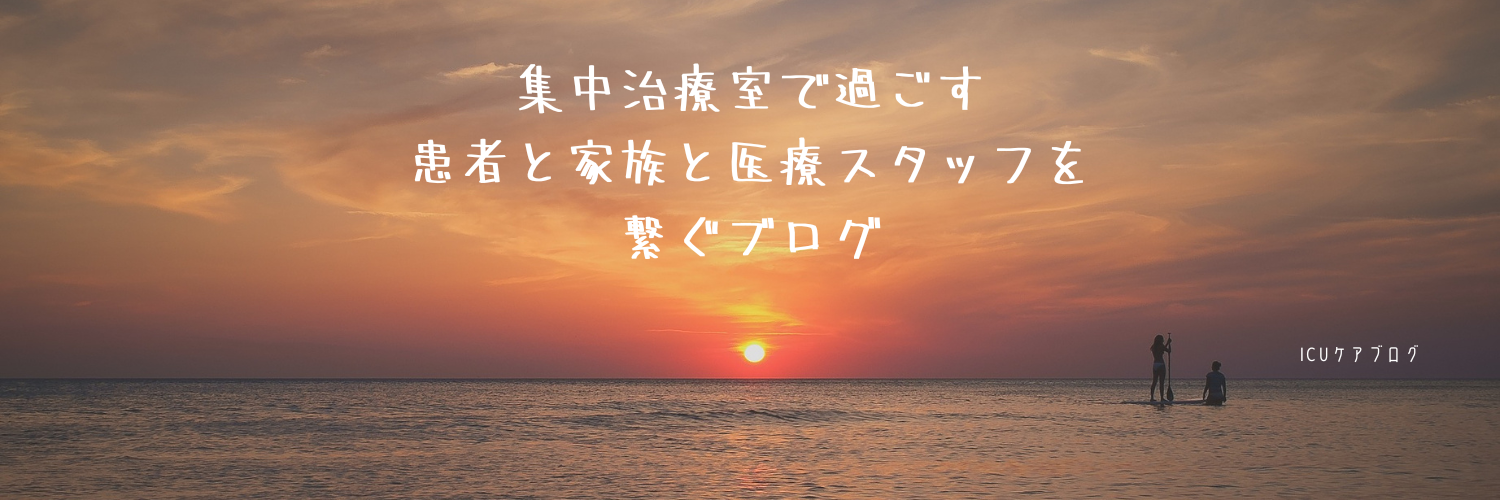
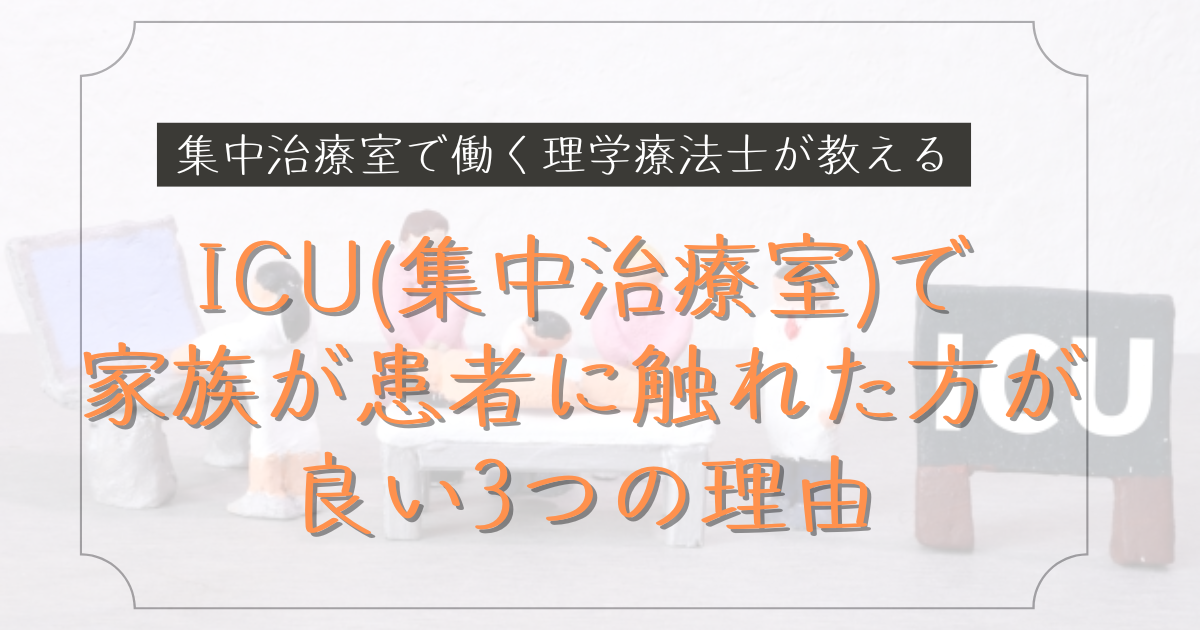

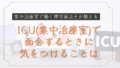
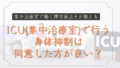
コメント