こんにちは、こたちです
株式投資を少しずつ始めた皆さんは、配当金をもらっている人も少なくないでしょう
しかし、複利の力を使うのであれば、もらった配当金はまた同じ会社に投資して、
さらにもらえる配当金を増やす、、、
こうやってお金を増やしていこう!!と考えている方は多いのではないでしょうか
しかし、私はもらった配当金はその年のうちに全て使うようにしています
もったいない気もしますが、そこは割り切っています
2024年は家族でディズニーランドのバケーションパッケージで散財してきましたし、
2025年は4泊5日の沖縄旅行も行くことにしています
せっかくもらった配当金だから、もったいなくて使えない?
そんなあなたに、もらった配当金は使うためにある!!その理由を解説していきます
配当金とは
そもそも配当金とは何でしょうか
私たちが株式を購入すると、私たちはその株式会社の株主になれます
株式会社は、株主から集めた資金をもとに、会社を運営し、利益を出します
その利益の中から、株主に対して年に数回、投資をしてくれたお礼を頂けます
これが配当金です
配当金の額は様々ですが、どんなに高くても投資額の5%が限度です
100万円の投資をしたら、年間5万円をもらえるわけですね
そして、この5万円は、いわゆる不労所得です
自分は働かず、お金に働いてもらって得たお金です
このようにして得た不労所得で暮らすことをFIRE(経済的自立)と呼んだりするわけですね
配当金を使った方がいい理由は、自分を精神的に安定させるため
結論から言うと、配当金を使った方がいい理由は
自分の人生を豊かにし、心の平穏を保ち、冷静に積立のインデックス投資を続けるためです
まず、皆さんはインデックス投資の相場を知っているでしょうか
全世界株式は、年間3-5%の成長が見込めることが過去の歴史からわかります
米国株式は、ここ数年好調だったこともあり、年間5-7%の成長が見込めます
つまり、インデックス投資に積立を長期的に続けることができれば、
特に考えることなく5-7%程度の利益が見込めるわけです
しかしそこには20%〜50%の暴落を乗り越えて、積立投資を続ける必要があります
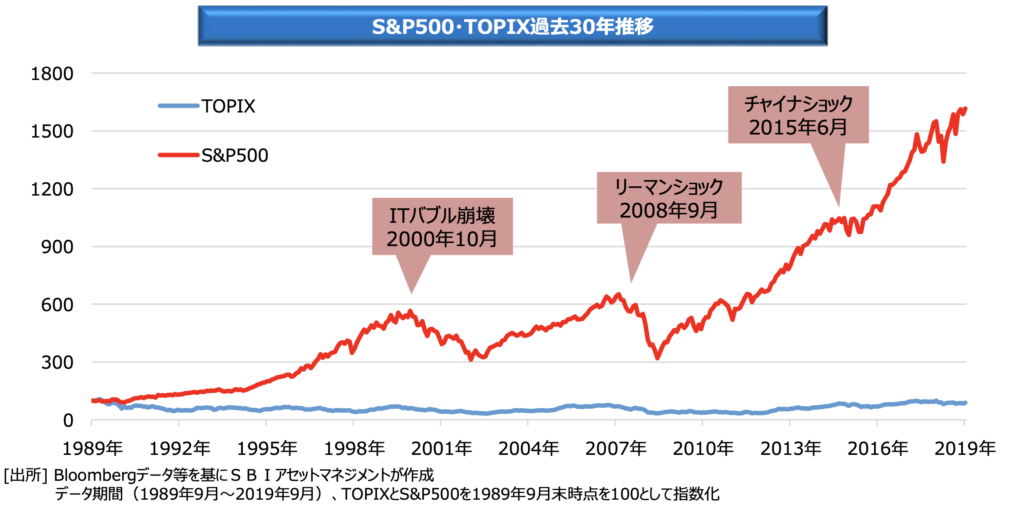
例えばリーマンショックの時期は、最高値から50%の暴落が起きました
リーマンショック前まで株価が戻るには3年近い月日が必要でした
皆さんは、自分の資産が一瞬にして半分になり、3年間もマイナス成長にも関わらず、
コツコツ積立投資を続けることは、本当に可能でしょうか?
2022年も約20%の下落局面がありましたが、その倍以上の暴落に耐えられるでしょうか?
もし耐えられないのであれば、インデックス投資だけでなく、
高配当株投資にも目を向けることを勧めます
高配当株投資とは、配当金が比較的高い4-5%の配当金を狙っていく投資スタイルです
日本株であれば楽天証券の楽天SCHDや、SBI証券のSBI・SCHDが良いでしょう
米国株であればシュワブ・米国配当株式ETF(SCHD)や、SPYD、LQDが良いでしょう
この辺りの銘柄に投資できれば、安定して投資額の4-5%の配当金が得られます
配当金は暴落が来てももらえます
株価が半分になっても、配当金だけはもらえます
非常にありがたい存在なのです
インデックス投資は5-7%で増えていくのですが、その果実を得るのはずっと先です
そこまで我慢できれば意味がありません
なぜなら暴落時こそ、積立投資を続けられなければ、安い値で株を買えないからです
ただ、50%の暴落が来ても、平然と株を買い続けることができる人は多くないでしょう
だからこそ、配当金をもらっておけば、心が落ち着くのです
インデックス投資を続けられるのです
配当金を何に使うもあなたの自由
配当金を得る、高配当株投資は、理論上、インデックス投資に劣ります
高配当株投資=4〜5% vs. インデックス投資=5〜7%
これが複利で増えるのですから、当然です
それでも心の安定のために、確実に、今、配当金を得る
それが高配当株投資の目的です
そこまで理解できれば、配当金は何に使ってもあなたの自由です
株価が暴落していれば、再投資するもよし
株価が安定しているなら旅行に行くもよし
趣味、思い出作り、旅行、大切な時間、、、
その時々で、心が最も安定することを目指して、使ってしまえばいいのです
それが、高配当株投資の目的なのですから
ちなみに私は、2023年は年間40万円、2024年は年間46万円の配当金がありました
私は無欲な人間なので、妻に40万で好きなことを計画して良い、と伝えると
旅行30万円と、家具10万円の購入をして、妻はウキウキしておりました
これが、私の、私の家族の心の平穏であり、最も大切なことなのです
皆さんにとって、最も幸せな配当金の使い方を、家族で考えるのもまた幸せなのかもしれませんね
以上、参考になれば幸いです!
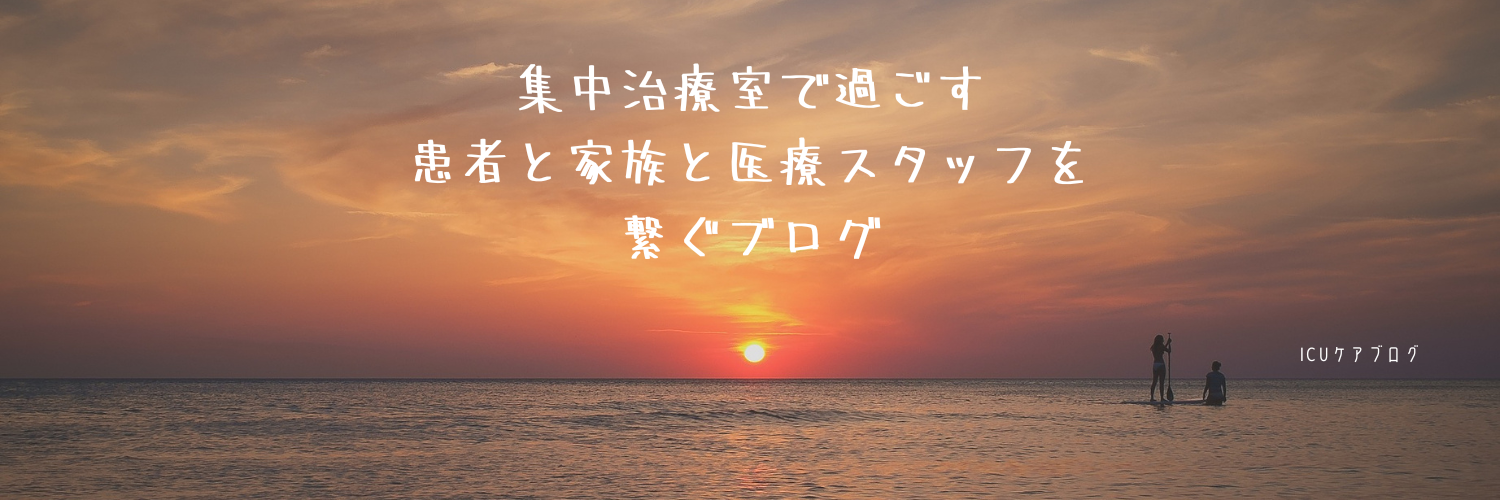
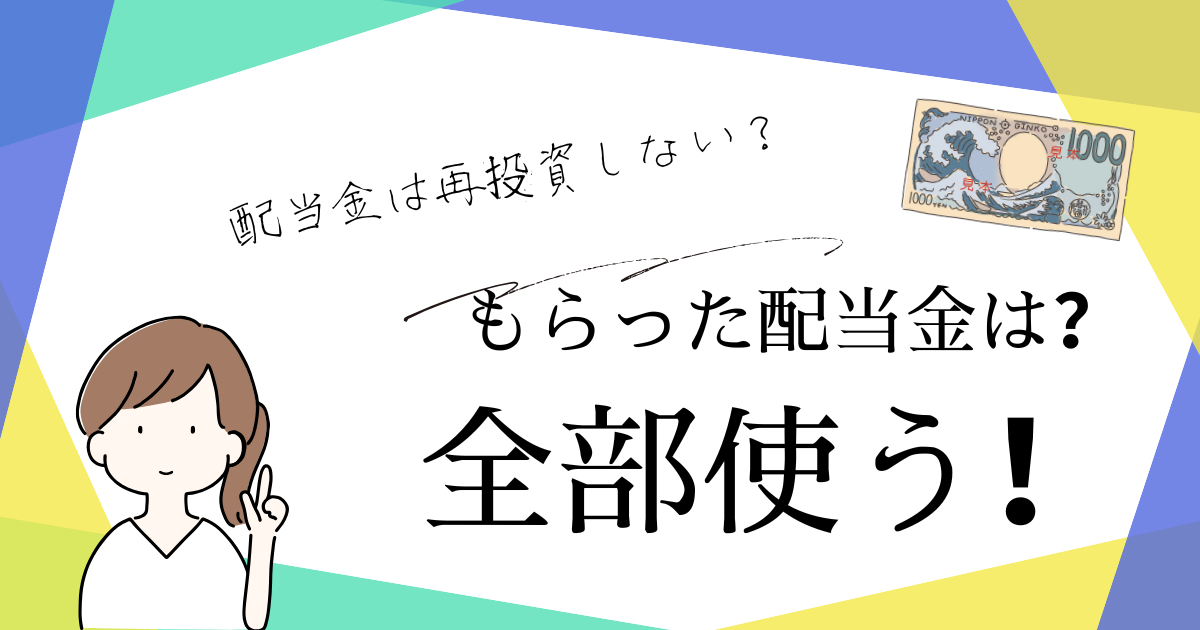
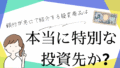

コメント